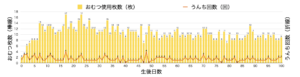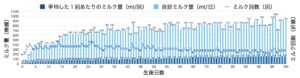こんにちは!『ちち』です。
今回は、我が家の『かわいこ』のお宮参りについて、成長日記も兼ねてお伝えします。
東京の中ではかなり穴場の神社だと思いますので、ぜひ御覧ください。
お宮参りとは? 昔からの文化と現代の意義
お宮参りとは、赤ちゃんが生まれて初めて神社にお参りし、健やかな成長を祈願する日本の伝統行事です。古くは「産土参り(うぶすなまいり)」とも呼ばれ、その土地の守り神である産土神(うぶすながみ)に赤ちゃんが無事に生まれたことを報告し、これからの成長を見守っていただく意味合いがあったようです。
『ちち』個人的には、赤ちゃんの成長を祝う家族のイベントとしての意味合いが強くなって来ているのかなと思っています。特に、普段は一緒に住んでいないおじいちゃん、おばあちゃんにとっては、孫の顔を見られる貴重な機会。家族の絆を深める良いきっかけにもなりますね。
我が家も、お宮参りは「かわいこ」の成長を祝う大切なイベントとして、そして家族みんなで思い出を作る機会として、ぜひ、と思い実施を決めました。
いつやる? お宮参りの時期と日取りの決め方
お宮参りの時期は、一般的に男の子は生後31日目か32日目、女の子は生後32日目か33日目とされています。しかし、これはあくまで目安。現代では、厳密にこの日数にこだわる必要はありません。
最も大切なのは、赤ちゃんとママの体調です。 産後間もないママの体調、そして赤ちゃんの体調を最優先に考えましょう。
次に、家族みんなの予定が合う日を選びましょう。特に、遠方からおじいちゃん、おばあちゃんが来る場合は、移動や宿泊の都合も考慮する必要があります。
お日柄(六曜)を気にする方もいるかもしれませんが、最近はあまり気にしない方も増えているようです。ただ、大安や友引などの吉日を選ぶと、より縁起が良いと感じる方もいるでしょう。
我が家の場合は、『かわいこ』と『はは』の体調、そして家族みんなの予定を考慮し、生後1.5ヶ月頃に実施しました。
どこでやる? お宮参りの場所選びのポイントと我が家の選択
お宮参りを行う場所、つまり神社選びですが、最初は特にこだわりはありませんでした。ただ、調べていくうちに考慮した方が良さそうな点がわかってきましたので共有します。
一般的なポイント
場所を選ぶポイントとしては、以下のような点が挙げられます。
- 家からの近さ: 生後間もない赤ちゃんや産後のママにとって、長時間の移動は大きな負担になります。できるだけ自宅から近い神社を選ぶのがおすすめです。
- アクセスの良さ: 公共交通機関を利用する場合は、駅からの距離や、バスの本数なども確認しておきましょう。自家用車の場合は、駐車場の有無や広さもチェックが必要です。ただ、外出に慣れていない時期なので、タクシーの利用も積極的に検討しましょう。
- 神社の由緒: 子どもの成長を願う神社として有名なのは、東京なら水天宮などが挙げられます。その他、安産祈願で有名な神社や、地域の氏神様なども人気があります。
もちろん、有名な神社でなくても、由緒ある神社はたくさんあります。
重要なポイント 「プライベート感」
ここまで一般的なポイントを書きましたが、我が家が重視したのは「プライベート感」でした。
有名な神社は、どうしても混雑しがちです。ご祈祷も、複数の家族や団体と一緒に行われることが多いと聞きます。
せっかくの機会ですし、可能であれば我が家だけでご祈願ができれば嬉しいですよね。
そこで我が家が選んだのは、代々木八幡宮です。
代々木八幡宮を選んだ理由
- 都心なのに緑豊か: 代々木八幡宮さんのHPを見ると、トップページに「都会に残る 緑豊かな鎮守の杜」と書かれています。文字の通り、都会の喧騒を忘れさせてくれるような、緑豊かな環境です。
- 比較的空いている: 隣には明治神宮がありますが、そちらは非常に混雑しているという噂。代々木八幡宮は、比較的落ち着いて参拝できる穴場スポットです。
- 1組ずつご祈祷していただける: これが最大の決め手でした。他の家族に気兼ねすることなく、我が家だけでご祈祷を受けられるのは、とても魅力的でした。
- 社殿での写真撮影が可能: ご祈祷を受ける方は、社殿内での写真撮影が許可されています。これは大きなメリットです!多くの神社では社殿内での撮影は禁止されているため、貴重な思い出を残すことができます。
実際に訪れてみると、緑豊かな境内はとても心地よく、厳かな雰囲気の中でご祈祷を受けることができました。『かわいこ』も、終始ご機嫌(ずっと寝てた)で、良い思い出になりました。


写真撮影はプロに頼むべき? 『ちち』の機会教訓
我が家は、プロのカメラマンに依頼せず、自分たちで撮影することにしました。
お金もかかるし、色々調整するのも大変かなと⋯
しかし、結論から言うと、プロのカメラマンに依頼するべきだったと思いました(笑)
プロに頼んだほうが良いと思った理由
- 準備でバタバタ: 赤ちゃんに祝い着(産着)を着せたり、抱っこしたりと、何かと準備に手間取り、写真撮影の準備は二の次。準備が完了したら他の参拝客に迷惑がかからないようにタイミングをみて撮る!⋯大変でした。
小さい三脚で苦戦していたら、近くのお兄さんが撮りましょうか?と言ってくれました。ありがとうお兄さん(笑) - おじいちゃん、おばあちゃんへの負担: 写真撮影をお願いしたおじいちゃん・おばあちゃんですが、慣れないスマホ操作に苦戦。結果的に、負担をかけてしまいました。
また、おじいちゃん、おばあちゃんのスマホは画質が少ないこともあるので、いいスマホで撮るようにしましょう(笑)
LINEで送ってあげればいいのです。 - カメラのスペック問題: スマホと比べても、やはりプロのカメラマンの機材には敵いません。
- 素人撮影の限界: 撮影した写真を見てみると、『ちち』の顔は日陰で暗く、『はは』と『かわいこ』は太陽の光で白飛び寸前…という残念な結果に。
その場ではバタバタしつつも「よし!いい感じに写真撮れた!」と思っていても、後から見返すと、やはり素人撮影の限界を感じる出来でした。
プロのカメラマンに依頼するメリット
- 高品質な写真: プロのカメラマンは、光の加減や構図など、細部にまでこだわって撮影してくれます。
- 撮影の負担軽減: 家族みんなが、撮影に気を取られることなく、お宮参りに集中できます。
- 思い出を美しく残せる: 一生に一度の記念日を、最高の形で残すことができます。
特に、お宮参りをやる目的の一つとして、子どもの成長記録として写真を残しておきたい!というのがあるならば、プロのカメラマンに依頼することを強くおすすめします。
調べてみると、予算に多少が余裕があればカメラマンのマッチングサイトなどがいいのではないかと思います。
ちょっと予算を抑えたいひとや、枚数制限なし!などの希望があれば、ココナラとかでも写真撮影を検討するといいです!
お金の話 ご祈祷料とお祝い、地域の風習を確認しよう
お宮参りには、ご祈祷料(初穂料)や食事代など、支払いのタイミングがいくつかあります。また、お祝いとしておじいちゃん・おばあちゃんからいただける場合もあるでしょう。
我が家の場合、ご祈祷料は我が家で用意し、食事代は『ちち』の親が出してくれ、お祝い金は両家からいただきました。
お祝い金やお祝いの品については、地域によって風習が異なる場合があります。事前に両家の両親に確認しておくと、トラブルを避けることができます。
まとめ:父親目線で考える、お宮参りの準備と心構え
お宮参りは、赤ちゃんにとっても家族にとっても、一生に一度の大切なイベントです。父親として、しっかりと準備を進め、家族みんなで素敵な思い出を作りましょう。
最後に、父親目線で、お宮参りの準備と心構えをまとめます。
- ママの体調を最優先に: スケジュールや場所選びは、ママの体調を最優先に考えましょう。
- 家族みんなで協力: 準備や当日の役割分担など、家族みんなで協力して進めましょう。
- 写真撮影はプロに依頼: 後悔しないためにも、プロのカメラマンに依頼することを検討しましょう。
- お金のことは事前に確認: ご祈祷料やお祝いなど、お金に関する慣習は事前に確認しておきましょう。
- 楽しむ気持ちを忘れずに: 何よりも、赤ちゃんの健やかな成長を願い、家族みんなで楽しい時間を過ごしましょう。
このブログが、これからお宮参りを迎えるご家族の参考になれば幸いです。